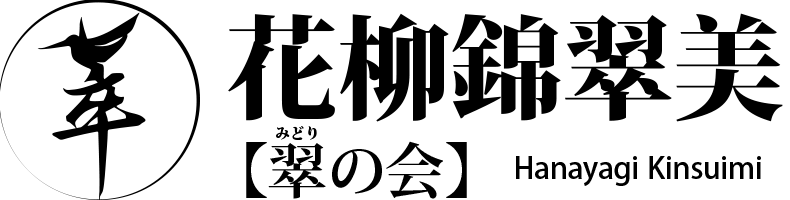長い長い時間をかけて
ゆっくりと凍っていったから
きっともう溶けることはないのだろうと思っていた。
このまま
人の息づかいが絶えてしまった屋敷のような
霙降る真昼の
火の気のない部屋の寝床のような
寂々とした湿った孤独を糧に肥大した心臓のまま
いつか
そんなに遠くないいつか
あっけなく幕が降りるのだろうと思っていた。
頭をよぎっていく古びた風景は
よく晴れた午後の校庭も
団欒の灯がともりはじめた頃の通学路も
なぜかずっとミュートがかかっていて
登場人物が皆呆けたように口をパクパク動かしている。
少しずつかみ合わない程度の狂気で
凍った心臓をやみくもに暖め続ける一方で
いつのまにか
いびつな暖かさより安定した冷たさに心地いい居場所を見つけていた。
あんなにも体温のない言葉で最期を見送ったあの人。
選択できない出会いの意味を
いまだに理解できずにいるあの人。
何も感じないまま
何もわからないまま
そんなものだと思っていた。
白に昇華されたまばゆい光の中で
解き放たれたように踊る誰かのシルエットが見える。
ドレスの裾をひるがえしながら
裸足で踊るシルエットが見える。
あれは
私なのか
私のような幻なのか。
まぶしくて
息がつまるほどまぶしくて
よくわからない。